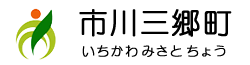いちかわみさと歴史探訪
市川三郷町には甲斐源氏発祥の地をはじめ、数多くの文化財があります。
この歴史探訪では、「広報いちかわみさと」で取り上げた文化財を第1編の「甲斐源氏旧趾」からカラー写真とともに紹介します。
第1編 町指定文化財 甲斐源氏旧趾(かいげんじきゅうし)
「武田」姓は義清が武田冠者(かんじゃ)義清と称し始まったという説、ともに配流された義清の子の清光(きよみつ)が平塩の地に土着してから「武田」姓が始まったとするなど諸説があります。
いずれにしても、義清・清光父子が非凡な武将であったかは、新天地を求めたこの平塩の地から「甲斐の武田」の名を後世に残していったことでも想像に難くありません。
【広報いちかわみさと2月号より(2015年)】
第2編 町指定無形文化財 手漉和紙技術の保持者 豊川秀雄(とよかわひでお) 氏
市川大門の手漉き和紙は「美人の素肌のように美しい」と例えられ、「肌吉紙(はだよしがみ)」と呼ばれ御用紙として幕府に献上されていました。
かつては200軒近くあった手漉き和紙の工場も、時代の移り変わりと共に減り、現在は豊川製紙6代目豊川秀雄さん、たった1人となってしまいました。
その豊川さんにも現在、後継者はいません。歴史探訪第2編では、市川大門手漉和紙の今と未来を考えます。
■先人を学ぶ
伝統文化に触れ、先人の知恵と努力を学ぼうと、市川小学校では卒業証書を自分の手で漉いています。この取り組みは豊川さんをはじめ、市川和紙技術研究会の協力のもと昭和57年から続いています。合併し、市川三郷町となった現在では、町内すべての小学校にこの取り組みは広がっています。
■先人を偲ぶ
役場本庁舎にほど近い、八乙女神明宮では、毎年7月の祭典で「市川紙づくり唄」(町指定無形民俗文化財)を披露し先人を偲んでいます。市川紙づくり唄保存会では後世へ保存継承を願い「紙漉き唄」「楮打ち唄」発祥の碑を昨秋、建立しました。
■繋げるために
伝統文化を絶やすまいと、市川三郷町商工会では人材育成講習会を計画し、技術・歴史を学び、将来の担い手を模索しています。
【広報いちかわみさと3月号より(2015年)】
第3編 国指定文化財 神獣鏡(しんじゅうきょう)
 明治27年、甲府盆地南西部 曽根丘陵の一角にあたる大塚地区の鳥居原狐塚古墳(とりいばらきつねづか)から、「赤烏(せきう)元年」と記され、周囲に神獣の文様のある「神獣鏡(しんじゅうきょう)」が発見されました。
明治27年、甲府盆地南西部 曽根丘陵の一角にあたる大塚地区の鳥居原狐塚古墳(とりいばらきつねづか)から、「赤烏(せきう)元年」と記され、周囲に神獣の文様のある「神獣鏡(しんじゅうきょう)」が発見されました。「赤烏」とは中国で三国志の時代、呉の国の年号で西暦238年にあたり、邪馬台国の卑弥呼が同じ頃、魏の国に使者を送っていた時期と重なります。
しかし、なぜ魏とは敵国であった呉の鏡が、なぜ内陸である山梨の古墳から出土されたのか、多くの謎が今でも明らかになっていません。
3世紀頃の大陸と日本の関係を考えるうえでも、きわめて貴重といえるこの鏡は国の重要文化財に指定され、現在、市川三郷町の一宮浅間神社から東京国立博物館に寄託されています。
【広報いちかわみさと5月号より(2015年)】
第4編 町指定天然記念物 双幹の欅(そうかんのけやき)
樹木の根回りは6,70m、高さは14mもあるこの大きな欅は、樹齢500年から600年と推定されています。
また、さらに珍しいことに、この欅の巨木は北側の根元に2体の石仏を抱きこんでおり、母親が子供をかわいがるような形をしているところからも、古くから子宝や安産の御神木として祀られてきました。
【広報いちかわみさと6月号より(2015年)】
第5編 町指定有形文化財 藤尾寺木造千手観音坐像(とうびじもくぞうせんじゅかんのんざぞう)
 この千手観音坐像は落居地区の光岳寺法堂(こうがくじほうどう)に隣接した藤尾寺の本像として祀られており、制作年代は衣文(えもん:衣装のひだ等の表現)などから鎌倉時代初期の「運慶」の影響を受けた仏師による鎌倉時代~室町時代にかけての作と推測されています。
この千手観音坐像は落居地区の光岳寺法堂(こうがくじほうどう)に隣接した藤尾寺の本像として祀られており、制作年代は衣文(えもん:衣装のひだ等の表現)などから鎌倉時代初期の「運慶」の影響を受けた仏師による鎌倉時代~室町時代にかけての作と推測されています。坐像の高さは108.6cm。これを立像に計算すると2m近くの高さで、かなり大きな仏像の部類になり、当時の人たちの願いの大きさと重なります。
【広報いちかわみさと8月号より(2015年)】
第6編 県指定文化財 大塚古墳(おおつかこふん)
_1.jpg) 大塚古墳は市川三郷町大塚にある北原古墳群の前方後円墳のひとつです。
大塚古墳は市川三郷町大塚にある北原古墳群の前方後円墳のひとつです。古墳の前方部から発掘された遺物は、六鈴鏡(りくれいきょう)、直刀を含め、石室内にあったものと想定されます。
この古墳の出土品において注目すべき点は、甲胃、刀剣などに見られる軍事的な要素の出土品と鈴釧(すずくしろ)、六鈴鏡に見られる呪術的な要素の出土品が併存して発見された点が挙げられます。
墳丘周辺の試堀調査によって、周溝の一部が発見されましたが、これによれば、本来の全長は50メートルを超えるのではないかと推測されています。
【広報いちかわみさと10月号より(2015年)】
第7編 町指定文化財 押切刑場跡及び青洲堤(おしきりけいじょうあとおよびせいしゅうづつみ)
初代市川大門村村長でもあった渡邊青洲(せいしゅう)<青洲は号、名は信>は明治40年の大水害に対して堤防工事に奔走し、堤を完成させました。
その完成を見ることなく青洲は亡くなりますが、人々はその偉業を讃えた桜を植え、「青洲堤植櫻之記」の石碑を作り「青洲堤」の名を後世に伝えようとしました。
【広報いちかわみさと11月号より(2015年)】
第8編 県無形民俗文化財 山田の神楽獅子(やまだのかぐらしし)
_0.jpg) この獅子舞は、今から300年ほど前、重兵衛という人が京で宮仕えをしたときに優雅な舞に魅せられ、その奥義を体得して郷里の村の若者に伝授し、小正月 1月14日の道祖神祭に舞ったことが始まりと伝えられています。
この獅子舞は、今から300年ほど前、重兵衛という人が京で宮仕えをしたときに優雅な舞に魅せられ、その奥義を体得して郷里の村の若者に伝授し、小正月 1月14日の道祖神祭に舞ったことが始まりと伝えられています。県の無形民俗文化財にも指定されたこの「山田の神楽獅子」は、現在では小正月に近い日曜日に集落の道祖神に初舞を奉納した後、厄年にあたる人の家や新築、結婚、出産などの祝い事のあった家を訪れることになっており、幾多の変遷を経ながら「山田神楽獅子保存会」の方々に今日も伝承されています。
【広報いちかわみさと1月号より(2016年)】
第9編 県指定有形文化財 表門神社の石鳥居(うわとじんじゃのいしどりい)
 三珠地区の表門神社にあり、県道市川大門線沿いに建つこの石鳥居は、横幅2.57mに対し高さもほぼ同じ2.64mという、他の鳥居では見られないような安定した形をしています。
三珠地区の表門神社にあり、県道市川大門線沿いに建つこの石鳥居は、横幅2.57mに対し高さもほぼ同じ2.64mという、他の鳥居では見られないような安定した形をしています。材質は石垣や石壁に多く用いられる安山岩(あんざんがん)で、ほぼ直立に近い柱など直線的に作られた数多くの特徴があります。
この石鳥居の作られた時代は鎌倉時代までさかのぼると推察され、町内でも最古の部類に入る県指定の文化財です。
【広報いちかわみさと2月号より(2016年)】
第10編 町指定有形文化財 熊野神社本殿(くまのじんじゃほんでん)
 熊野神社は甲府盆地を見下ろす小高い平塩の岡、そのほぼ中央に建立されています。平塩地内の諸神(もろがみ)を集め祀ったと伝えられており、本殿は材質や手法などから、江戸時代末期までに造られたものと推定されています。
熊野神社は甲府盆地を見下ろす小高い平塩の岡、そのほぼ中央に建立されています。平塩地内の諸神(もろがみ)を集め祀ったと伝えられており、本殿は材質や手法などから、江戸時代末期までに造られたものと推定されています。本殿の壁面に見られる彫刻も見事なもので、東面は「翁の図」、北面は「鍛冶師の図」、西面は「大蛇成敗の図」があり、脇障子(突き当たりに立てられた仕切り)には「昇龍・降龍」の透彫(すかしぼり)も施されてあります。
【広報いちかわみさと4月号より(2016年)】
第11編 町指定有形文化財 紙本淡彩釈迦涅槃図(しほんたんさいしゃかねはんず)
 涅槃図(ねはんず)とは釈迦が沙羅双樹の木の下で入滅したといわれる光景を描いたもので、宮原地区にある本定寺のこの涅槃図は、紙本淡彩(紙に薄く色をつけること)で描かれた縦2.09m、横1.35mの大きな絵図です。
涅槃図(ねはんず)とは釈迦が沙羅双樹の木の下で入滅したといわれる光景を描いたもので、宮原地区にある本定寺のこの涅槃図は、紙本淡彩(紙に薄く色をつけること)で描かれた縦2.09m、横1.35mの大きな絵図です。日順という僧が元禄5年(1692年)に描いたことが記されており、無銘の作品が多い仏画の中で、年代と作者が明確である点からも貴重な作品です。
【広報いちかわみさと5月号より(2016年)】
第12編 県指定天然記念物 一瀬桑の親株(いちのせくわのおやかぶ)
益吉はこれを原苗として、自らの桑園で増やし近隣の村に配布しました。
これは葉の質、収穫量ともに従来の桑とは明らかに異なり、病害虫にも強い優れたものでした。大正5年に行われた西八代郡農会主催の「桑園品評会」に出品、さらに同年大日本蚕糸会山梨支会主催の「第三回蚕糸品評会」において受賞し、益吉によって見出されたこの桑はまたたく間に日本全国に普及していきました。
【広報いちかわみさと6月号より(2016年)】
第13編 町指定文化財 帯那峠と石龕(せっかん)
昭和10年11月に帯那トンネルが開通するまでは、山保地区さらに河内地区の人々にとって、この峠道の持つ意義は大きいものでした。
昔は人も馬も山を越える事は大変なことであり、山道の安全平穏を願い峠などに神を祀ることが古くから行われていました。帯那峠では大きな石龕を作り、この中に馬頭観音と蚕影明神を祀りました。
【広報いちかわみさと7月号より(2016年)】
第14編 町指定文化財 高前寺梵鐘(こうぜんじぼんしょう)
 鴨狩津向地区にある高前寺の梵鐘は江戸初期明歴2年の鋳造で、当時の名工と言われた「府中(甲府)在住の沼上主水助吉次・同弥左衛門尉吉久」親子の作とあります。
鴨狩津向地区にある高前寺の梵鐘は江戸初期明歴2年の鋳造で、当時の名工と言われた「府中(甲府)在住の沼上主水助吉次・同弥左衛門尉吉久」親子の作とあります。梵鐘にはひとつの民話があります。旧鰍沢町の丸屋という呉服屋が身延山久遠寺に釣鐘を寄進することにしました。釣鐘を納める日、船は富士川を下ったが浅瀬に乗り上げ、沈んでしまいました。すると水の中から「コーゼンジニイタイ」と声がし、釣鐘は高前寺に納められました。何も知らない村人はいつしか"横取りの鐘"と呼ぶようになったそうです。
【広報いちかわみさと8月号より(2016年)】
第15編 県有形文化財 六鈴鏡(ろくれいきょう)
 市川三郷町大塚地区の大塚古墳から出土した5世紀頃の鏡です。
市川三郷町大塚地区の大塚古墳から出土した5世紀頃の鏡です。六鈴鏡は青銅製で直径11.45㎝。縁に同1.95㎝の鈴が六つ付き、裏面は鏡になっており、鏡と鈴の両方を意識して作られたものと考えられます。神聖な祭祀の際、巫女が腰に付け、動きに合わせて音を鳴らしたとみられ、鈴の中には小石が入っていて「シャラシャラ」という音色が生み出される特殊な呪具と考えられます。
平成6年の発掘調査で出土し、武具などの出土品とともに平成9年、県文化財に指定されました。
六鈴鏡レプリカは、役場本庁舎ロビーにあります。1500年前の音色再現。実際に手に持って、鳴らしてみて下さい。
【広報いちかわみさと9月号より(2016年)】
第16編 町指定有形文化財 熊野神社の大クヌギ
 平塩の岡にある熊野神社は、北側が急斜面で南側が緩い傾斜になる丘上にあります。
平塩の岡にある熊野神社は、北側が急斜面で南側が緩い傾斜になる丘上にあります。境内の東南部にある大クヌギは、主幹は垂直的に北東方向に伸び、樹高19.3m、根廻り幹囲4.7mと、クヌギとしては、まれに見る巨樹です。
クヌギは、椚・櫟・橡・櫪などの字があてられ、野山に自生し雑木林をつくる場合が多く、単木であることはとても珍しい様態です。
【広報いちかわみさと10月号より(2016年)】
第17編 県指定有形文化財 浄善寺鰐口(じょうぜんじわにぐち)
 鰐口は仏堂の正面の軒下などに架けられている金属製の仏具で、横から見ると鰐の口に似ていることからこのように呼ばれるようになりました。
鰐口は仏堂の正面の軒下などに架けられている金属製の仏具で、横から見ると鰐の口に似ていることからこのように呼ばれるようになりました。落居地区にある浄善寺の鰐口は、銅製で県指定の文化財は二口(2個)あり、 両面の外帯にそれぞれ(表)「甲州大中寺鎮守天神宮」、(裏)「応永第十年五月初四日」の刻銘がみられます[応永は1394年~1428年]。
県内の在銘品の中でも古作で、室町時代の初期を代表する美術的価値の高い工芸品です。
【広報いちかわみさと12月号より(2016年)】
第18編 町指定有形文化財 浄身石(じょうしんせき)
 県道四尾連湖公園線の途中、集落の手前に『川』という場所があります。
県道四尾連湖公園線の途中、集落の手前に『川』という場所があります。巨岩の隙間から湧水が絶え間なく流れており、この清水を貯えた池のほとりに、出産児の乳児に良く似た形の浄身石(別名産婦浄身石)があります。
この石は木花咲耶姫(このはなさくやひめ)が、富士山の噴火から難を逃れるため四尾連湖へ向かう途中、陣痛が起こり、この『川』にて無事出産、浄身石に座って身を浄めたと伝えられています。
【広報いちかわみさと1月号より(2017年)】
第19編 町指定有形文化財 南村の宝篋印塔(ほうきょういんとう)
三珠地区の大塚南区にあるこの塔は、高さ4.2 メートルに及ぶ大きなもので、天明二年九月(1782 年)に建立されたものです。大きな笠が塔身全体を覆い、塔身も台をはさみ上下二段に分かれ「宝篋印塔」の文字が刻まれています。
菊や牡丹などの彫刻も美しい、安定感のある塔です。
【広報いちかわみさと4月号より(2017年)】
第20編 町指定有形文化財 大塚邑水路新造碑(写真:左) 代官中井清太夫生祠(写真:右)
 大塚河原は大雨が降るたび、水路の水が笛吹川から逆流し、田圃は水没してしまいました。村人は水路を西に向け、水を笛吹川の下流へ流そうと考えましたが、途中に押出川が横切っていました。甲府代官の中井清太夫は押出川の下に樋を埋めて水を通す計画を指導し、天明6年(1786)から翌年にかけて大改修が行われました。
大塚河原は大雨が降るたび、水路の水が笛吹川から逆流し、田圃は水没してしまいました。村人は水路を西に向け、水を笛吹川の下流へ流そうと考えましたが、途中に押出川が横切っていました。甲府代官の中井清太夫は押出川の下に樋を埋めて水を通す計画を指導し、天明6年(1786)から翌年にかけて大改修が行われました。感謝した村人は清太夫を生神として祀り、石碑を立てて功績を刻もうとしましたが、清太夫はこれを許しませんでした。「大塚邑水路新造碑」が建てられたのは清太夫退官後の寛政9年(1797) のことです。現在の水路も当時と同様に押出川の下を通っています。現在は大塚の県営排水機場の北隅に移されています。
【広報いちかわみさと6月号より(2017年)】
第21編 町指定有形文化財 いぼ地蔵
 高田公民館の東にある地蔵です。地蔵の顔を石でこすり、石の粉をイボに塗ればとれるとされたことからこの名が付きました。また「オコリ病」にもご利益があったといい、明治8年(1875年)の記録には「地蔵の顔は深い穴が開いていて、半俵の供養田があったものを民有地に編入し、庭には石臼を飛石に使い、像の後ろに梅樹が植えられていた」などと書かれています。
高田公民館の東にある地蔵です。地蔵の顔を石でこすり、石の粉をイボに塗ればとれるとされたことからこの名が付きました。また「オコリ病」にもご利益があったといい、明治8年(1875年)の記録には「地蔵の顔は深い穴が開いていて、半俵の供養田があったものを民有地に編入し、庭には石臼を飛石に使い、像の後ろに梅樹が植えられていた」などと書かれています。地元では一休和尚が開眼したものを、元治2年(1865年)に再建したと伝えられています。
【広報いちかわみさと8月号より(2017年)】
第22編 町指定有形文化財 表門神社本殿(うわとじんじゃほんでん)
 表門神社は御崎神社、あるいは市川文珠とも称される延喜式内社で、祭神は天照大神、倉稲魂命(ウガノミタマノミコト)、瓊瓊杵命(ニニギノミコト)の三神です。
表門神社は御崎神社、あるいは市川文珠とも称される延喜式内社で、祭神は天照大神、倉稲魂命(ウガノミタマノミコト)、瓊瓊杵命(ニニギノミコト)の三神です。本殿は永保年間(1081~1084)を初めとして数回の造営記録がありますが、現在の建物は棟札によって元禄8年(1695)の建立であることがわかっています。
三間社流れ造りで、今は銅版で覆われていますが、当初は檜皮葺でした。獅子、鶴、鳳凰等の動物の彫刻が精巧に施されたうえ、彩色がなされ、正面扉は金箔張りです。元禄8年の棟札には「大工石川久左衛門 脇同五郎右衛門重良」と記されており、下山大工の作であることが知られます。またこの時に拝殿、神楽殿、随神門、鳥居も建立されており、境内の景観を一新したものと思われます。
【広報いちかわみさと9月号より(2017年)】
第23編 町指定有形文化財 六地蔵石幢(ろくじぞうせきどう)
 地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の六道で衆生(しゅじょう)を救済するという六地蔵信仰は室町時代に一般化し、六地蔵が刻まれた石幢(石塔の一種)が各地で造立されるようになりました。
地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の六道で衆生(しゅじょう)を救済するという六地蔵信仰は室町時代に一般化し、六地蔵が刻まれた石幢(石塔の一種)が各地で造立されるようになりました。印沢地内にあるこの石幢は基礎の上に幢身を載せ、その上に中台を置き、中台の上に6体の地蔵を刻んだ龕部(がんぶ)(仏像などを納める部分)を安置。その上に笠と宝珠を載せてあります。龕は破損していますが笠をしっかり支えています。無銘ですが室町時代の様式と思われます。
【広報いちかわみさと11月号より(2017年)】
第24編 町指定有形文化財 大 乗寺五輪塔(だいじょうじごりんとう)
 五輪塔は塔婆の一形式で主に供養塔、墓標として使われました。下から地輪、水輪、火輪、風輪、空輪の石を積み重ねていますが、この五輪塔は風輪、空輪が失われており、別の石塔のものが乗せてあります。水輪には梵字の「バ」
五輪塔は塔婆の一形式で主に供養塔、墓標として使われました。下から地輪、水輪、火輪、風輪、空輪の石を積み重ねていますが、この五輪塔は風輪、空輪が失われており、別の石塔のものが乗せてあります。水輪には梵字の「バ」が刻まれています。火輪以下の高さが約1mあり、大きなものといえます。『甲斐国志』に「大乗寺ノ境内ニ荒墳一基ヲ存セリ、里人岩間殿ノ墓ト称シテ香花を供ス、其ノ古事ハ伝ハラズ」とあります。
岩間殿についての史料はほとんどありませんが南北朝時代の岩間の領主とも伝えられています。この五輪塔も形態の上から、南北朝時代のものとしておかしくありません。
【広報いちかわみさと12月号より(2017年)】
![]() 町教育委員会学術文化係 TEL:055-272-6094
町教育委員会学術文化係 TEL:055-272-6094