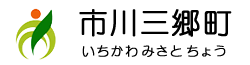ホーム > 暮らしの情報 > 国民健康保険 > 医療費が高額になったとき
医療費が高額になったとき
高額療養費とは
病気やケガで医療機関に支払った1ヶ月の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として払い戻されます。該当される方には申請書を送付します。
※申請書の送付は概ね療養のあった月の3ヶ月後となります。
※令和5年4月から、高額療養費の支給申請手続きの簡素化を開始しました。
簡素化の申請をすると翌月以降から毎回の申請は不要となり、指定口座へ自動振込となります。
高額療養費支給申請手続きの簡素化について.pdf![]() (91KB)
(91KB)
高額療養費支給申請手続簡素化申出書.pdf![]() (486KB)
(486KB)
自己負担限度額
【70歳未満の方】
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
|---|---|---|
| ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
| イ | 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
| ウ | 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
| エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円〈44,400円〉 |
| オ | 住民税非課税 | 35,400円〈24,600円〉 |
〈 〉内は同じ世帯で、療養のあった月を含む過去12ヶ月で4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額となります。
〇 所得区分は総所得金額等から住民税の基礎控除を引いた後の金額となります。
〇 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。認定証が必要な方は町民課または各支所の窓口で交付申請をしてください。
※マイナ保険証をご利用の場合、認定証は不要です。
〇 所得の申告がない場合は所得区分アとみなされますのでご注意ください。
【70歳未満の方の自己負担額の計算方法】
〇医療機関ごとの一部負担金が21,000円を超えるものが対象となります。ただし、入院・外来・医科・歯科は別計算になります。
〇保険診療でないものや食事代、差額ベッド代等は対象外です。
【70歳から74歳の方】
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 入院 | 世帯単位 | ||
| 現 役 並 み 所 得 者 (※1) | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> | ||
| Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円> | |||
| Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> | |||
| 一般 | 18,000円(※4) | 57,600円 <44,400円> | ||
| 低所得者Ⅱ(※2) | 8,000円 | 24,600円 | ||
| 低所得者Ⅰ(※3) | 8,000円 | 15,000円 | ||
※1 現役並み所得者とは、同じ世帯で国民健康保険に加入する70歳以上の方に、1人でも課税所得が145万円以上の方がいる場合に適用されます。ただし、これらの方の収入の合計額が520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満。国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は520万円未満)の場合は、申請により、1割または2割負担となります。なお、該当される方には申請書を送付します。
〈 〉内は同じ世帯で、療養のあった月を含む過去12ヶ月で4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額となります。
※2 低所得IIとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方です。
※3 低所得Iとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方です。
※4 年間(8月~翌7月)の外来の限度額は144,000円となります。所得区分が一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の自己負担額の合計に適用します。該当される方には申請書を送付します。(高額療養費の簡素化の申請をしている場合は自動振込となります。)
〇 現役並み所得者Ⅱ・Ⅰに該当する場合は「限度額適用認定証」を、低所得者Ⅱ・Ⅰに該当する場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。認定証が必要な方は町民課または各支所の窓口で交付申請をしてください。
※マイナ保険証をご利用の場合、認定証は不要です。
【70歳から74歳の方の自己負担額の計算方法】
〇金額にかかわらず、すべての医療費の一部負担金を合算できます。
〇外来の一部負担金は個人ごとにまとめますが、入院を含む一部負担金は世帯で合算します。
〇保険診療でないものや食事代、差額ベッド代等は対象外です。
【70歳未満の人と70歳から74歳の人を合算する場合】
①70歳から74歳未満の人の限度額をまず計算
②①に70歳未満の人の自己負担額を加算
③70歳未満の人の限度額を適用して計算
国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証
申請により交付した「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、ひと月の医療機関ごとの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。(食事代等がある場合は、別途自費負担として、上乗せして請求されます。)
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請した月の1日から適用されます。
※同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別になります。
申請に必用なもの
●国民健康保険の資格を確認できるもの(以下①~③のうちいずれか1つ)
①交付を希望する方の国民健康保険被保険者証(70~74歳の方は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)
②国民健康保険資格確認書
③国民健康保険資格情報のお知らせ
●世帯主と交付を希望する方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
●申請される方が別世帯の場合は、申請者の顔写真付き身分証明証
注意点
●課税世帯の70~74歳のうち適用区分「現役並みⅢ」と「一般」の方は、被保険者証兼高齢受給者証を
医療機関に提示すると、医療機関での支払いが自己負担額までとなります。(申請が不要の方)
●国民健康保険税に滞納がある場合や所得の確認ができない方(未申告等)がいる世帯は、認定を受けら
れない場合があります。
●有効期限は、毎年7月31日となります。引き続き限度額適用(・標準負担額減額)認定証が必要な方は、
8月以降に改めて申請をしてください。
※郵送での申請を希望される方は、下記のお問い合わせ先までお電話ください。
申請書
●限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書![]() (65KB)
(65KB)
●限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書記入例![]() (369KB)
(369KB)
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請が不要になります
これまで限度額適用(・標準負担額減額)認定証は申請により交付していましたが、マイナンバーカードを保険証として利用することにより限度額適用(・標準負担額減額)認定証がなくても限度額が適用されるようになります。
※マイナンバーカードを保険証として利用するには事前登録が必要となります。
※医療機関でマイナンバーカードを読み取る機器を導入していない場合は、従来どおり限度額適用(・標準負担額減額)認定証の提示が必要となります。
お問い合わせ先
町民課 国保年金係
TEL:055-272-1105 FAX:055-272-1198
![]()