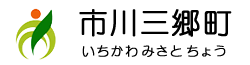ホーム > 暮らしの情報 > 国民健康保険 > 後期高齢者医療保険制度
後期高齢者医療保険制度
後期高齢者医療保険制度について
後期高齢者医療保険とは
後期高齢者医療保険制度は、対象となる高齢者の方々も自ら保険料を負担することで、高齢者医療の担い手である現役世代の理解をいただきながら、後世に高齢者の医療制度を引きついでいく「支えあい」の制度です。
制度運営の主体となるのは、山梨県後期高齢者医療広域連合です。保険資格の決定や保険証の発行、保険料の決定など、医療保険事業の要となる「保険者」になります。
町は、保険証の配布や各種申請等、保険料の徴収、制度全般についての相談など、町民の皆様の直接の窓口としての役割を持っています。
病気やけがの治療を受けたとき、かかった医療費の1割(一定の所得者は2割、現役並み所得者は3割)を自己負担します。
一か月に支払った自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
また、所得が低い世帯には、保険料の軽減や医療費の自己負担限度額の引き下げ、入院時食事代の減額認定など、負担を軽くする制度があります。
加入する方
75歳以上のすべての方は、年齢に到達する誕生日から自動的に加入します。
また、65歳以上74歳までの一定以上の障害がある方は、本人の申請により加入することができます。
お医者さんにかかるとき
| 所得要件等 | 窓口負担割合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 課税所得※1が145万円以上で、医療費の窓口負担が3割の方 | 3割(世帯全員) | |||
| 上記以外の方 | 世帯内のすべての被保険者※2が、課税所得 28万円未満の方 | 1割(世帯全員) | ||
| 上記以外の方 | 世帯の被保険者が1人の場合 | 「年金収入※3+その他合計所得金額※4」が200万円未満の方 | 1割 | |
| 「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上の方 | 2割 | |||
| 世帯の被保険者が2人の場合 | 「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円未満の方 | 1割(世帯全員) | ||
| 「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円以上の方 | 2割(世帯全員) | |||
※1 「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。
※2 「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方となります。
※3 「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入です。また、公的年金等控除を差し引く前の金額となります。
※4 「その他合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
後期高齢者医療保険料
保険料は、前年度の所得により、7月1日に決定されます。(本算定といいます。)
年金から天引きされる「特別徴収」の方には、4月に仮徴収として4・6・8月分の支払を通知し、7月に本算定として年間保険料の決定と10・12・2月分の支払をお知らせします。
保険料を現金または口座振替で納付される「普通徴収」の方には、7月の本算定時に年間保険料の決定をし、納入通知書をお送りいたします。納期は、7・8・9・10・11・12・1・2月の8回です。納め忘れのないようにお願いいたします。
葬祭費
5万円を喪主の方にお支払いたします。
手続きには、身分証明及び喪主であることの証明になるものが必要です。(葬祭時のハガキ・火葬場の領収書・新聞の葬祭欄など)
届出
世帯に異動があった場合は必ず14日以内に届出をしてください。
| こんな時は届出を | 手続に必要なもの | |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険に加入するとき | 町外から転入したとき | 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許、パスポートなど) |
| 一定の障害を持つ65歳以上75歳未満の方が加入を希望したとき | 身分証明書、障害者手帳または障害年金証書 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 身分証明書、保護廃止決定通知書 | |
| 後期高齢者医療保険を脱退するとき | 町外に転出するとき | 身分証明書、保険証 |
| 65歳以上75歳未満の方の障害が基準の等級より軽くなったとき | 身分証明書、障害者手帳または障害年金の廃止(休止)通知など障害の程度が軽くなったことが分かるもの | |
| 被保険者が死亡したとき | 身分証明書(相続人やご家族様)、保険証、死亡を証明するもの、印鑑(相続人やご家族様) | |
| 生活保護を受け始めたとき | 身分証明書、保険証、保護開始決定通知書 | |
| その他 | 転居・氏名変更をしたとき | 身分証明書、保険証 |
| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分証明書、汚れて使えなくなった保険証 |
お問い合わせ先
町民課
TEL:055-272-1105 FAX:055-272-1198
![]()