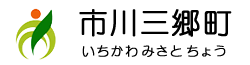ホーム > 観光情報 > 史跡・文化財 > 市川紙づくり唄(町指定無形民俗文化財)
市川紙づくり唄(町指定無形民俗文化財)
 【指定年月日】平成21年10月12日
【指定年月日】平成21年10月12日【保持団体】 市川紙づくり唄保存会
和紙づくりの長い伝統をもつ市川大門の町に江戸時代から紙づくりの仕事唄として唄い継がれてきたのが「紙漉き唄」と「楮(かぞ)打ち唄」です。昭和30年代の頃から和紙づくりも手漉きから機械化され、これらの唄も次第に唄われなくなってきました。
~市川紙漉き唄~
この唄がいつの時代から唄い始められたか、誰が曲を作り、作詞したのかはわかりません。和紙づくりは、様々な技術的、自然的な条件から冬の厳しい寒い季節が仕事の中心となります。こうした、つらい仕事を紛らす為や仕事の合間の休息の時や、祝い事の宴席などに唄われたものと思われます。
~市川楮(かぞ)打ち唄~
「かぞ」とは、古くから和紙の原料として用いられてきた桑科の植物です。正式名は「こうぞ」で、「かぞ」はこの地域の方言的な呼称です。この木の表皮の部分を剥いで、アルカリ液(昔は灰液)で煮て柔らかくし、漂白して平らの石、或いは、硬い板の上で、棒で叩いてほぐし、繊維を取り出して紙の原料としました。この細かく叩きほぐす際の作業を「楮打ち」といいます。この作業は連続的で速いテンポで行なう為、唄もこれに合わせて、速い節まわしでできています。
![]()