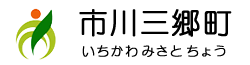文化財(彫刻)
文化財(彫刻)
熊野神社の狛犬
 この神社の本殿前にある一対の石造狛犬(こまいぬ)は、前足が折れているが、これはもと那知社にあったもので「応永12乙酉2月1日」 (1405)の刻銘をもち、年号をはさんで右に「大公性見」左に「小公藤二良と示されている。高さ一尺三寸余(42cm余)硬質な安山岩製、一見はなはだ古風なこの狛犬は前足を前に張り、顔を正面に向けて突っ立つ東大寺式のものとは相違して、体を前方にぐっと乗り出した形態はむしろ犬に近い、顔面の様子といい、極度に太い前脚といい、粗削りの感がある。しかし首に垂れ毛、尾の盛り上がった旋毛の具合などから、笑えない古拙への親しみがわく。
この神社の本殿前にある一対の石造狛犬(こまいぬ)は、前足が折れているが、これはもと那知社にあったもので「応永12乙酉2月1日」 (1405)の刻銘をもち、年号をはさんで右に「大公性見」左に「小公藤二良と示されている。高さ一尺三寸余(42cm余)硬質な安山岩製、一見はなはだ古風なこの狛犬は前足を前に張り、顔を正面に向けて突っ立つ東大寺式のものとは相違して、体を前方にぐっと乗り出した形態はむしろ犬に近い、顔面の様子といい、極度に太い前脚といい、粗削りの感がある。しかし首に垂れ毛、尾の盛り上がった旋毛の具合などから、笑えない古拙への親しみがわく。古い時代のものは、その例少なく熊野神社の狛犬は、在銘遺品としては全国的にも屈指のものである。東大寺の石獅子をへだたること約三百年、この間に日本化されたというよりは、むしろ別系統と見るべく、狛犬の原始型を知る上に重要な遺物である。「大公性見」 「小公藤二良」はこれを作った「大工」を「大公」と書き「小工」を「小公」としたのである。これは「石工」を「石巧」と記した天明2年の長昌院の宝匡印塔(南区)と同様であろう。木造建築に限らず、金属工芸でも、石造美術関係でも同じことであるが、製作者を「大工」といい、そのもとに「小工」があって実際の仕事に当たった場合が多い。
上述のごとく、狛犬の原始型であり、しかも在銘としてはわが国屈指という点後世に伝えたい逸品である。(山梨県政六十年誌から)
千手観世音菩薩像/不動明王像/昆沙門天王像

千手観世音菩薩像(中央)/不動明王像(右側)/毘沙門天王像(左側)
- 千手観世音菩薩像
- 千手観世音菩薩像は、木造の寄木造立像、像高146cm、台座、蓮華座高さ40cmで、頭部に十面の観音像を頂き、左右に四六腎を有し、それぞれの手に仏の知恵を現わす仏具を持つ。
- 不動明王像
- 不動明王は、木造の寄木道立像千手観世音菩薩像の向かって右側に脇待として安置してある。像高は70cm、台座、光背含む、高さ118cmで、右手には剣、左手には羅索を持つ。
- 昆沙門天王像
- 毘沙門天王像は、木造の寄木道立像であり、千手観世音菩薩像の向かって左側に脇侍として安置してある。像高は77cm、台座光背含む高さ114cmで、右手には宝棒、左手には宝塔を持ち、足下には悪鬼を踏みつけている。
十二神将像


像は間口二門奥行三門の瓦ぶきであり、堂内に安置してある十二神将は十二体あるが手足に損傷があり又持ちものの武器等破損しているがほぼ完全の状態で保存されている。
薬師瑙璃光如来像/日光菩薩像/月光菩薩像

薬師瑙璃光如来像(中央)/日光菩薩像(右側)/月光菩薩像(左側)
- 薬師瑙璃光如来像
- 毘沙門天王像同様像は間口二門奥行三門の瓦ぶき堂内に安置してある薬師如来像は顔面の一部が損傷ある。
薬師如来像の台座の裏には、朱墨で元禄の年号と数名が今日も判読出来る。ヌメの所に行基作の銘もある。
伝説によると元禄12年9月8日県下大洪水で神金村(現在塩山市)雲峰寺の境内の薬師堂が倒壊し洪水のため流失し旧上野村字矢作の矢作田へ流入したのを当時の人々が引き揚げ仏像の為禅昌寺に祀り現在に至ったものと伝えられている。 - 日光菩薩像
月光菩薩像 - 脇師の日光・月光菩薩に神将は江戸末期、京都の仏師より購入したと伝えている。
日光菩薩像は、木造寄木道立像で像高70cmである。
月光菩薩像は、木造寄木造立像で像高77cmである。
![]()