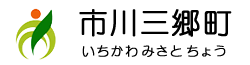浄善寺鰐口
浄善寺鰐口について
鰐口は社殿や仏堂の正面の軒下に架けられた金属製の具です。横から見ると鰐の口に似ていることからこのように呼ばれるようになりました。
浄善寺の鰐口は、銅製で三口保存されており、このうち二口は県指定の文化財です。

左の鰐口は無銘ですが、古式のもので、すぐれた技術を見せています。
形態その他から14世紀の制作と推定さてます。面経18.0cm・縁厚5.4cm・胎厚7.0cmであり、撞座の備えがあります。
右の鰐口は先年まで境内の七面堂に懸けられていました。銅製で面経16.2cm・縁厚4.5cm・胎厚5.5cmほどで、形態がよくととのっています。表裏面に同心円をえがく数条の圏線が鋳出されていますが、撞座の設けはなく制作年代の特色をしめしています。両面の外帯にそれぞれ次の刻銘がめられます。「甲州大中寺鎮守天神宮」(表)「応永第十年五月初四日」(裏)県下でも在銘遺品の中では上位に位する古作で、作風もすぐれて美しく、室町時代の初期を代表する美術的価値の高い工芸品であります。
浄善寺きんす
 「甲州落居山大中寺宝建久八丁巳季」の銘があります。文化財の指定は受けていないが、今後、より総合的な調査、検討の要がります。
「甲州落居山大中寺宝建久八丁巳季」の銘があります。文化財の指定は受けていないが、今後、より総合的な調査、検討の要がります。
- 【種類】
- 町指定工芸
- 【所在地】
- 市川三郷町落居6137番地
- 【管理者】
- 浄善寺
- 【指定年月日】
- 昭和58年12月7日
![]()