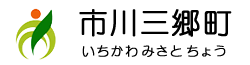県指定文化財
県指定文化財
表門神社の石鳥居
 この鳥居は春日型で全体の構成が直線的に作られ、反りの少ない笠木、島木の両端は垂直に切られている基礎上に建てられ、一見転びの認められない太い円柱は、双方とも中辺で接合され、その幅柱真々2.57mに対し、鳥居の総高2.64mという、全く後世の造建とは解されない背の低い安定感に富んだ造構である。
この鳥居は春日型で全体の構成が直線的に作られ、反りの少ない笠木、島木の両端は垂直に切られている基礎上に建てられ、一見転びの認められない太い円柱は、双方とも中辺で接合され、その幅柱真々2.57mに対し、鳥居の総高2.64mという、全く後世の造建とは解されない背の低い安定感に富んだ造構である。柱上に台輪を添えた点、春日鳥居としては規格外であるが、その他にも楔を欠くなど新しい要素が僅かながら混在する。
元来台輪は柱の上部から侵される腐食防止のためであったが、それを必要としない石造では、この様式の残存がたまたま、柱と島木との調和保持の用へと転移したのであろう。
この雄大な木割幅に対する背の低いこと、直立に近い柱、島木笠木の先端の切り方など一種の風格を存した逸作で造建は鎌倉時代、材は安山岩である。
一瀬桑の親株
 赤木
赤木根周り 98cm 地上36cmの部位で二枝となり、北側の一枝はその幹囲42cm 南側の一枝は幹囲43cmでその樹高は約4mである。
 青木
青木南側のものは根囲り66cm 地上68cmの位置にこぶがあり、その部位での幹囲は62cm 高さは約3.5mである。北側のものは地上55cmでの幹囲が88cmその上部にて幹囲40cm大の三枝に分かれている。樹高は約4mである。
一ノ瀬桑の由来
明治31年ごろ旧上野村川浦の一瀬益吉が、中巨摩郡田富村(旧忍村)の桑苗業者から購入した桑苗(品種鼠返し)のうちから、本来の鼠返しとは異った性状良好なる固体を発見し、これを原苗とした。代出苗を繁殖母体として自己の桑園を造成するとともに村内と近村にも配布した。
大正5年に行われた、西八代郡農会主催第一回桑園品評会に一瀬氏の桑園が桑の収量、葉質ともに抜群であることが認められ、さらに同年の大日本蚕糸全山梨支会主催「第三回蚕糸品評会」においても、優等賞が下賜され養蚕界の注目を浴びるに至った。
一瀬氏によって選出されたこの桑苗に性状がいく分異なる二つの種類があった。
一つは条(枝)の伸長が梢長く、古条(秋期落葉後の枝)が青い灰色を帯び、他の一つは条長が短かい半面、葉の着生が密で、古条の色は赤味を帯びている。
このことから前者を白鼠、後者を赤鼠と呼んでいたが、後に「一瀬桑」と命名されてからは、白鼠を一瀬の青木、赤鼠を赤木と呼び変えられることになった。
「一ノ瀬」の命名は選出者の一瀬の姓をそのまま冠したものであり、全国的に普及されるに至って、農林省は全国の共通名を「一ノ瀬」とすることに統一したが、本県では前記の蚕糸品評会のさい「一瀬桑」として出品されたことから現在においても「一瀬桑」と呼ばれている。
薬王寺のオハツキイチョウの雄株
 山梨はオハツキイチョウの宝庫であり、葉上に種子をつける雌株は八本ほど見つかっていて、そのうち身延町下山の上沢寺のオハツキイチョウは明治24年7 月、白井光太郎博士によって葉上に種子のできる事実をこの木によって発見され、学界に紹介された木で、その隣りの本国寺のオハツキイチョウとともに昭和4 年4月、国指定の天然記念物に指定された。
山梨はオハツキイチョウの宝庫であり、葉上に種子をつける雌株は八本ほど見つかっていて、そのうち身延町下山の上沢寺のオハツキイチョウは明治24年7 月、白井光太郎博士によって葉上に種子のできる事実をこの木によって発見され、学界に紹介された木で、その隣りの本国寺のオハツキイチョウとともに昭和4 年4月、国指定の天然記念物に指定された。葉上に葯をつけるオハツキイチョウの雄株は、同町上八木沢(前記上沢寺の富士川の対岸)の山神社の境内にあり、明治29年4月17日、藤井健次郎博士によって発見され、これも珍奇なものとして広く欧米の学界に紹介され、昭和15年7月国の天然記念物に指定された。オハツキイチョウの雄株で指定されたものはこの木だけである。
ここ薬王寺にあるオハツキイチョウの雄株は、山神社の境内にある木についで二番目に発見された木である。発見者は旧三珠町誌の編集にたずさわっていた山梨植物同好会々長の秋山樹好先生で、発見当時(昭和51年)の「植物採集ニュース」にも掲載された
この木は寺の境内の南西側にあり、根本の周囲4.1m、目通り幹囲3.7m、枝張り東7m。西9m。南6m、北6.5m、樹高16mでかなりの大木である。葯の数が多い葉ほど変形が著しく、葉も小さくなる。また葯をつけた葉は一枚一枚落ちるのではなく、葉と雄花と葯をつけた葉とが叢生したまま落ちてくるのである。
表門神社のコツブガヤ
 根廻り3.1m、樹高約19.5m、目通り幹囲2.2m、枝下3.5m、枝張は東6.6m、西6.3m、南7.6m、北5.4mである。
根廻り3.1m、樹高約19.5m、目通り幹囲2.2m、枝下3.5m、枝張は東6.6m、西6.3m、南7.6m、北5.4mである。この特色は枝条が密生、葉は短小で先端は鈍で母種(基本種)ほど鋭くない。最大の特徴は「コツブガヤ」と同定される重要な決めてとなる種子が極めて少ない点にある。下幹部の南側に多少の腐れはあるが、樹勢はすこぶる旺盛で、またよく実をつける。
大塚古墳
 三珠町大塚、北原古墳群中の一基。前方後円墳であるが、帆立貝式古墳とみなされることもある。周囲を削平されているが、現状では全長40m、後円部径35mで、後円部の高さは5mである。
三珠町大塚、北原古墳群中の一基。前方後円墳であるが、帆立貝式古墳とみなされることもある。周囲を削平されているが、現状では全長40m、後円部径35mで、後円部の高さは5mである。前方部石室より鈴釧、六鈴鏡、短甲、挂甲小札類、直刀、小札類、鉄鏃などの副葬品が発見された。また、後円部においても竪穴式石室が存在することが確認されている。
前方部の石室は全長3m、幅0.8m程で、床面には赤彩された小石が敷かれている。
通常、前方後円墳では後円部に石室が築かれるが、本古墳のように前方部にも石室が築かれる例は珍しい。
墳丘からは茸石、円筒埴輪、土師器、須恵器が発見されている。
墳丘周辺の畑での試掘調査によって周溝の一部が発見されているが、これによれば本来の全長は50mを超えるのではないかと思われる。
大塚古墳出土資料一括739点
大塚古墳は、三殊町大塚北区北原に所在する前方後円墳である。かつて、鏡、刀剣が出土したことが知られているが、それらは現在所在が不明である。
前方部から発掘された遺物は、耕作時に発見された六鈴鏡、直刀を含め、石室内に遺存していたものと思われる。
この出土品において注目すべきことは、甲胃、刀剣などに見られる軍事的要素と鈴釧、六鈴鏡に見られる呪術的要素が併存している点である。
なお、本古墳の年代は5世紀末あるいは6世紀初頭と考えられる。

鈴釧、六鈴鏡
- 鈴釧
- 本体長径14.6cm 短径11.5cm 内径7.6cm×5cm
- 六鈴鏡
- 径11.45cm 鈴径1.95cm
- 桂甲
- 長さ7cm弱 幅3cm弱のものが多い
- 短甲
- 高 前胴高33cm 後胴高41cm
幅 前胴押付板部29cm 後胴押付板部48cm - 直刀
- すべて欠損品 最低五振 身幅は約4cm
- 馬具
- 鉄製楕円鏡板付き轡の破片
- 鉄鏃
- 玉類 埴輪 土師器 須恵器
![]()