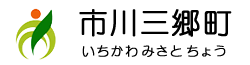ホーム > 観光情報 > 史跡・文化財 > 文化財(建造物)
文化財(建造物)
文化財(建造物)
表門神社
表門神社は、御崎(ミサキ)神社あるいは市川文珠とも称され、延喜式内社で由緒ある神社である。祭神は天照大神、倉稲魂命(ウガノミタマノミコト)、瓊々杵命(ニニギノミコト)の三神である。
 本殿
本殿「甲斐国志」には、永保年間(1081~4)を初めとして数回の造営記録があるが、現在の建物は棟札によって元禄8年(1695)の建立であることがはっきりしている。
本殿は三間社流れ造りで、今は銅板で覆われているが当初は檜皮葺きである。蟇股(カエルマタ)・脇障子・手挟等に獅子・鶴・鳳凰等の動物の彫刻が精巧に施されたうえ彩色がなされ、正面扉には金箔が貼られている。
棟札には大工とうりょう、石川久左衛門家久わき大工同五郎左衛門重良と記されており、下山大工の作であることが知られる。
文化15年(1818)に屋根替が行なわれているが、他に大きな改変部分はなく、当初の形態をよく残した江戸中期を代表する建造物である。
 神楽殿
神楽殿本殿と同じく元禄8年の造立である。この時に今も残る拝殿・随神門・鳥居も一緒に建てられており、境内の景観を一新したものと思われる。
正面一間、側面一間、切妻造檜皮葺(現在銅板葺)のこの建物は木鼻の湯紋や形態をみると本殿と同一であり、同時期の建物であることがはっきりわかる。
毎年2月第一日曜日(以前は2月第一の酉の日)の例祭には、この神楽殿で約900年前から受け継がれている。町指定文化財「太々神楽」が奉納される。
薬王寺
 後陽成院第八ノ宮良純親王御座所
後陽成院第八ノ宮良純親王御座所薬王寺は天平18年(746)聖武天皇の詔勅により、行基が開き観全僧都(カンゼンソウズ)の開山になる名刹である。
当寺の客殿の上段の間には、八之宮良純親王御座所(御座の間)の一部が保存されている。親王は、後陽成天皇の第八皇子で18歳で得度仏門に入り京都知恩院の門跡となったが、寛永20年(1643)12月事情あって甲斐に流され、興因寺(甲府市)に12年間、続いて明歴元年(1655)に当寺にうつり5年間住んだ後、万治2年(1659)6月許されて京都に帰り、寛文9年(1669)66歳で没した。
当寺はその後焼失したが享保2年(1719)に再建にかかっている。そのなかで親王の遺跡を保存するため御座の間(親王が居住した一部)を客殿のそばに移築し享保9年(1726)に完成したことが袋戸棚の裏面に当山十九世(桓龍(カンリュウ))によって記録されている。
御座の間は客殿の上段の間(通称宮さん座敷)から東側に床を一段高くして移築してある。御座の間は方一間二畳敷で、天井には直径1mの十三弁の菊花紋がかたどられている。上段の間とは御翠廉で仕切られていておもむきがある。また、知恩院門跡尊超法親王の筆になる「儼然」 の額が揚げられていて落ち付きがあり、気品が感じられ往時をしのぶにふさわしいものである。
親王が、使用した品々の多くは、帰京の折持ち帰ったが、京についてから供の者をとおして当寺へ下げ渡しになった物が何品かある。現存する物は、町指定文化財「硯」をはじめ見台、脇息、網焼物菓子器、丁子風呂(香をたきこめる道具)等が保存され親王をしのぶよすがとなっている。
光勝寺の仁王門
 仁王門は、梁行二間、桁行三間半の茅葺木造建築である。一間半の参道をはさみ、左右に仁王尊(金剛力士像)が一体づつ安置されている。
仁王門は、梁行二間、桁行三間半の茅葺木造建築である。一間半の参道をはさみ、左右に仁王尊(金剛力士像)が一体づつ安置されている。金剛力士像は、木造の寄木造立像で、身体赤色、上半身裸の力士が肘を張り、腕に力を漲らせ、衣装をなびかせ、怒った眼光と盛り上がる筋肉が隆々として写実の妙を示している。
右側は阿像(開口)木造の寄木造立像で像高は214cm、右手は開き伏せ、左手は三股杵を振り上げ、顔は右側を向いている。
左側は、吽像(閉口)木造の寄木造立像。像高は220cm、光背含む高さは228cmで、右手は肩の前で開き左手は握り伏せ、顔は左側を向いている。
南村の宝篋印塔
 塔の一種で、基檀の上に方形の塔身を置き、上に宝形造りの段状の笠石(屋根)を置き、相輪を立て笠石の四隅に隅飾りの突起があるのが特徴で塔身の四面には仏菩薩を標示する梵字などを刻む種子があるのが一般的である。
塔の一種で、基檀の上に方形の塔身を置き、上に宝形造りの段状の笠石(屋根)を置き、相輪を立て笠石の四隅に隅飾りの突起があるのが特徴で塔身の四面には仏菩薩を標示する梵字などを刻む種子があるのが一般的である。この塔は現高4.2mに及ぶ大きなもので、天明2年9月(1782)に念仏講中53人の発願で、惣村中が施主となって建立されたものである。
形式として通例なものでなく、大きな笠が塔身全体を覆う開いたものになっている。
塔身も台をはさみ上下二印に分かれている。また、塔身の月輪に当たる部分(種子)には梵字はなく宝篋印塔の文字が刻まれている。
菊と牡丹、蚯竜などの彫刻も美しく、全体的に調和のとれた安定感のある堂々たる塔である。
![]()