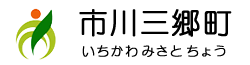ホーム > 観光情報 > 史跡・文化財 > 文化財(絵画・書籍・工芸・考古資料)
文化財(絵画・書籍・工芸・考古資料)
文化財(絵画・書籍・工芸・考古資料)
文殊画像
 伝えるところによると白河天皇永保元辛酉年(1081)主上が御病気で、大法秘法、典薬医術もその効なくたいへんな御なやみであった。ちょうどそのころ市川の神主が上京中であり、洛中で占いの評判が高かったので、御所に召し出されて、占いを申しあげ祈念すると、たちまち御病気が平癒せられたので、叡感斜ならず、後日社頭末社に至るまで御造営下され、また弘法大師作といわれる梵字で書いた文珠菩薩の画像をいただいたのである。このことによって以後この神社名が表門神社というより「おもんじ」さんの方が一般の人たちの愛称で呼ばれることになった。
伝えるところによると白河天皇永保元辛酉年(1081)主上が御病気で、大法秘法、典薬医術もその効なくたいへんな御なやみであった。ちょうどそのころ市川の神主が上京中であり、洛中で占いの評判が高かったので、御所に召し出されて、占いを申しあげ祈念すると、たちまち御病気が平癒せられたので、叡感斜ならず、後日社頭末社に至るまで御造営下され、また弘法大師作といわれる梵字で書いた文珠菩薩の画像をいただいたのである。このことによって以後この神社名が表門神社というより「おもんじ」さんの方が一般の人たちの愛称で呼ばれることになった。文珠は本来仏教の「文殊師利菩薩」の略称で、常に釈迦の左脇に侍して智恵、智識を司り、右に侍する普賢菩薩といってこれを普通釈迦三尊仏というのである。このようなことから智識、学問勉強ということで庶民信仰に発展したものである。
この画像は紺地に金泥で描かれ、線の所は梵字が書かれているが、極めて小さい梵字であるため何経が書かれているのかわからない。
八ノ宮遺物の絵馬


絵馬は通常、神社仏閣等に馬の絵を書いて奉納したことから名が出たものであるが、薬王寺の絵馬は特大のもので絵馬というよりは壁画を思わせるほど大きなもので、縦2.5m横2.5mもあり、雄大なものである。二面のうち向かって右のものは絵がはげ落ちている。
絵巻物
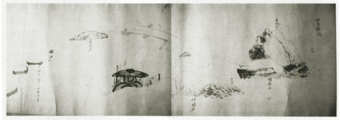 この絵巻物は、前記八ノ宮の遺作であり、墨絵で青墨を用いて庭園の配置等を描いたものである。石の配置、池の形、その石の名は仏教の四天王を配する等、古庭園の布置を示すものである。中に書いてある文はお家流で中々読み下し難いが次のようである。
この絵巻物は、前記八ノ宮の遺作であり、墨絵で青墨を用いて庭園の配置等を描いたものである。石の配置、池の形、その石の名は仏教の四天王を配する等、古庭園の布置を示すものである。中に書いてある文はお家流で中々読み下し難いが次のようである。法親皇良澄安通ノ御所ニスエサセ給図、として日本式庭園の石の配置図が描いてあり、その間に人皇八十六代後堀河の帝は守貞親王の皇子、御治世は十一年にしてくらいをゆづらしたまひ、をなじく八十七代の皇子、四条の院みことのが、堀河先帝ハ和歌の道にみこころをよさせ給ひしによりはじめて景をうつし、いしをつみ口むらさめの前庭とし給し可哉
自是いしに おもてをつけさせ給ひ 又は三蔵石とも 五行とも 八十一石とも 二十八宿とも 又は七星石ともなづけ給ひをくに国師のいわく、名あってかたちなし、千(変)万花(化)とのたまひぬ
良純親皇様が再び京にお帰りになったら、自分のお住居の御所安通院に理想の庭園をえがかれた(計画)ものと思考せられる。
大塚村絵図
 縦125cm、横140cmで、貼り合せた和紙に青、黄、茶、緑、灰の五色を用いて大塚村絵図が描かれている。
縦125cm、横140cmで、貼り合せた和紙に青、黄、茶、緑、灰の五色を用いて大塚村絵図が描かれている。折目が多少摩滅しているが、色採は鮮明で保存状況はよい。
この絵図は、塩島家に代々伝わるもので宝永五子年9月に委細を吟味のうえ書き上げたことが記されていることから西暦1708年江戸時代中期のもので、当時の大塚村落の状況を伺い知ることができる貴重な絵図であ
る。
御朱印状写
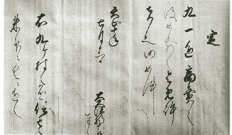 高萩区にある御朱印状とは、武田信玄公下付のものと、徳川家康公下付の九一色商売の一章と、徳川公が九一色衆と称する十七騎にくだされた都合三章とに、この三章の預り証の都合四枚からなっている。
高萩区にある御朱印状とは、武田信玄公下付のものと、徳川家康公下付の九一色商売の一章と、徳川公が九一色衆と称する十七騎にくだされた都合三章とに、この三章の預り証の都合四枚からなっている。武田の時代九一色郷民は山村なるによって納税をしない御伝馬役を仰せつかった。信玄の時代となり隣接の諸国に遠征がしげくなるにつれ、御伝馬役の九一色郷民は常に馬をもって兵站線の確保に当たっていたことが実に苦痛であった。
天正5年正月早々、駿河の今川家の家臣久島弥太郎が小曲村で事を構えたので、命によって高萩の地頭内藤肥前守が九一色の郷民を召し集め、正月2日桜峠に出陣、弥太郎これに恐れをなし逃げるところを追撃、翌3日富竹河原に追い詰め高萩村の渡辺甚右衛門これを打ち取ったので信玄の御感不斜ならず、翌2月20日高萩村高(光)源院へ御入り遊ばされ、御褒美としてなんなりとも望むものをとのことに、先年御下し置かれ候無納の御墨付を差し上げ奉り、百姓相続出来るように御願い申し上げたところ、引き替えに諸役御免許の御朱印を頂戴仕ると、すなわち武田家の御未印である。
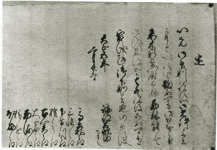 次は天正10年3月武田家城亡により、徳川家康は甲州治定のため2回目の入国を、同年6月9日駿州根原村より本栖、精進と来たが、大風雨のため精進に帯留、12日雨も漸く収まったので九一色衆十七騎の者ども百姓を督励して橋や道路を修復し、わずか二里の山坂を漸く昼頃古関村の吉祥寺で昼食をとり、阿難坂を越え夕暮れに上曽根竜華院にお泊まりになつた。
次は天正10年3月武田家城亡により、徳川家康は甲州治定のため2回目の入国を、同年6月9日駿州根原村より本栖、精進と来たが、大風雨のため精進に帯留、12日雨も漸く収まったので九一色衆十七騎の者ども百姓を督励して橋や道路を修復し、わずか二里の山坂を漸く昼頃古関村の吉祥寺で昼食をとり、阿難坂を越え夕暮れに上曽根竜華院にお泊まりになつた。この時の労を賞して御褒美として、なんなりとも所望せよとのおうせに、実は信玄公より下しおかれた御未印を御覧に入れたところ「諸商売役免許」の御朱印を下し置かれあり難く云々、と
その後この朱印については、本栖の地頭渡辺囚獄佐(ひとやのすけ)の申すに、「この御朱印は民家に預け置くは恐れ多い故、我等方に預け置くように」とのことで、寛永18年囚獄佐に預けその代償として「諸商売役免許」の鑑札を渡したのは天和2年(天正10年を去る百年後)代官平岡治郎右衛門が赴任してからである。 武田家の御朱印
武田家の御朱印
次に右御朱印は民間において恐れ多いというので、地頭渡辺囚獄佐が預ったが、囚獄佐がのちに江戸に転勤して持ち去ったので、九一郷の代表者が下げ渡しを陳情に行ったが下げ渡されず、かえって没収された形となり、その預り証が交付されたその写しとともに高萩の宝蔵に在ったものを、明治38年ここに役場を移す時、高萩区が接収し今日に至っている。
八ノ宮遺品の硯
 八ノ宮の遺品には、脇息、茶腕、菓子器、硯、等数多い品が残されている。中でも町指定の硯は、硯の海の向うに唐犬が浮きぼりに彫刻してあり硯全体が巻もののようなそりをもっており、色は幾分茶渇色を帯びている。
八ノ宮の遺品には、脇息、茶腕、菓子器、硯、等数多い品が残されている。中でも町指定の硯は、硯の海の向うに唐犬が浮きぼりに彫刻してあり硯全体が巻もののようなそりをもっており、色は幾分茶渇色を帯びている。
考古資料
 歌舞伎文化公園内の民族資料館がある。
歌舞伎文化公園内の民族資料館がある。ここに収められている資料は縄文、弥生、古墳の各時代のもので、これらの時代の生活文化のあとを示す土器や石器、古墳の副葬品が集められており、ことに弥生から土師器の資料は系統的に豊富に集まっている。
狩猟時代から原始農耕時代へと、古代文化の中心地をなした大塚地区を物語る豊富な資料館である。
石器頬は石斧(打製、磨製)石皿、凹石、石棒、石匙、石鏃、多凹石などである。また土器については縄文期の加曽利E式土器のほぼ完全なものを始めとして、主として中期、後期の破片を多数収めている。弥生時代の土器は完全なものが多く、初期、中期、後期のものが数十点収められている。また土師器、須恵器も完全な形で、数点が収められている。その他、弥生住居跡出土の炭化米や、古墳より出土の副葬品である直刀、馬具など、特筆すべきものがある。
![]()