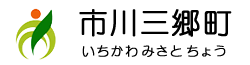ホーム > 観光情報 > 史跡・文化財 > 文化財(民俗資料・無形天然記念物)
文化財(民俗資料・無形天然記念物)
文化財 (民俗資料・無形天然記念物)
富くじ


天正10年3月、武田氏攻略のため駿河の国より富士川沿いに徳川家康が入国。表門神社を本陣に定められたことにより御朱印が下され、代々の将軍からも御朱印頂戴、幕府保護下に社頭の修復を行って来たが、幕府も時には台所の不如意もあって中々修復金の下げられない時もあった。
特に文政のころになると、財政もひっ迫し修復金も蹴られる始末に、別当内膳はそのころ関西で流行し始めた富くじによって修復をと思い立ち、当社奉行土井大炊頭に願い出でたところ、文政12年11月27日御許可をいただいた。
上野や市川辺では「くじ」もあまり多く売れないので、甲府山田町、甲斐奈神社を借りて三ヵ年間にわたって興行した。
年数度三ヵ年にわたっての興業だったが、文書によると思わしい成績も上らず、「よって拠ない場所のみ修復仕置候」とあり、その時使用した富くじの箱があり、中には板札、突槍等一切が保管されている。
甲州で富くじを興行したのは他にもう一ヵ所あるという。以上によって今の宝くじの前身「富くじ」が文政(1818~1829)のころ町内で発売されたことに意義があろう。
表門神社の太々神楽
 社伝によると、太々神楽のはじまりを鎮座以来とし、特に後世、甲斐守に任じ平塩岡に館居した逸見冠者源義清が鎮守として崇敬し、館中に神輿を迎え、神楽を奏して御台所祭を行って以来、毎歳かならずこれを行い社威を隆盛に赴かせたいといい、甲州でもっとも古い神様であると称されており、また義清の第三子清房は、市川氏の始祖となり、代々この神社に仕え、現宮司市川行房氏はその後裔であるという。始祖清房は源頼朝に愛され、しばしば鎌倉との間を往来しており、そのため太々神楽に鎌倉風の影響があるといい、さらに永保中、白河天皇の勅願所となった関係から京都とも往来、自ら京風の影響もうけているとも説かれているが、この舞は岩戸開きを中心にした神話を仕組んだいわゆる岩戸神楽であって、かって二十四座に及んだものがいまはそれが集合されて十三座をかぞえるだけである。
社伝によると、太々神楽のはじまりを鎮座以来とし、特に後世、甲斐守に任じ平塩岡に館居した逸見冠者源義清が鎮守として崇敬し、館中に神輿を迎え、神楽を奏して御台所祭を行って以来、毎歳かならずこれを行い社威を隆盛に赴かせたいといい、甲州でもっとも古い神様であると称されており、また義清の第三子清房は、市川氏の始祖となり、代々この神社に仕え、現宮司市川行房氏はその後裔であるという。始祖清房は源頼朝に愛され、しばしば鎌倉との間を往来しており、そのため太々神楽に鎌倉風の影響があるといい、さらに永保中、白河天皇の勅願所となった関係から京都とも往来、自ら京風の影響もうけているとも説かれているが、この舞は岩戸開きを中心にした神話を仕組んだいわゆる岩戸神楽であって、かって二十四座に及んだものがいまはそれが集合されて十三座をかぞえるだけである。昔は年中祭礼七十五度、そのうち2月初の酉の日11月初の酉の日をいまも大神事としている。
それは、義清がはじめて館中に神輿を迎え、神楽を奏したのが酉の日であったことにもとづくものと伝えられ、また4月3日の祭礼には神輿が芦川を渡渉して市川三郷町御崎明神の御旅所へ神幸するが、これには神楽衆が供奉し、同所拝殿で神楽を奏することはいまも行われている。
 神楽の舞人はもと砂田大隅はじめ社家神人によって行われ、世々これが承継されてきたものであるが、明治維新後、その退転してのちは氏子がかわり、舞人となる条件としては、各戸長男に限るとされ、いまも別火潔斎して奉任することはかわらない。
神楽の舞人はもと砂田大隅はじめ社家神人によって行われ、世々これが承継されてきたものであるが、明治維新後、その退転してのちは氏子がかわり、舞人となる条件としては、各戸長男に限るとされ、いまも別火潔斎して奉任することはかわらない。神楽には、強弱緩急による誇張した表現はないが、抑揚悠々、典雅な奏楽のまにまにそれぞれの衣裳と面をつけ、一切無言、鈴並に各種の取物を以って手振、身振によって神に奉任する真心を以って優雅、荘重に演舞し時に勇壮闊達なものもあり、またいわゆる段物として諧謔、瓢逸のものもある。
奏楽は7種類を数え、主として太鼓、編太鼓、笛を用い、面の現存するもの24種類に及ぶが、それに伴う舞技、奏楽の全部を伝えるものなく現今はその3分の2を演ずにすぎない。
- ◆舞の構成
- 一、扇の舞 / 二、剣の舞 / 三、国固の舞 / 四、大海原蛭子の舞 / 五、御崎の舞 / 六、天の岩戸の舞 / 七、大蛇退治の舞 / 八、弓の舞 / 九、祝詞の舞 / 十、奉剣鍛造の舞 / 十一、酒宴の舞 / 十二、国乱れの舞 / 十三、懲魔の舞 / 十四、終演の舞
大ケヤキ
 樹齢不詳 根本周囲8.8m 目通り4.8m 樹高20m
樹齢不詳 根本周囲8.8m 目通り4.8m 樹高20m樹盛は旺盛である。
巨木、古木にして、古くより「皿吊るしの欅」として地域住民に親しまれてきた。
地域住民の方の話によると、双幹の巨木であったが昭和22年頃の風水害の際、主幹の片方が根本近くで折れてしまった。樹齢は不詳であるが、よく風水害に耐えた古木である。そばに新羅三郎義光を祀ったと伝えられる義光明神の石祠がある。
石祠には、「きく神さん」とも呼ばれるが、「きく」という語から耳の神様として信仰されるようになり、耳の悪い人は皿に穴をあけて、その穴に縄を通し、大ケヤキに吊して耳が良くなるよう祈ったものだという。
このことから、この大ケヤキが「皿吊しの欅」と呼ばれるようになったのである。
![]()