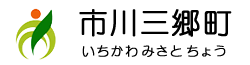ホーム > 観光情報 > 史跡・文化財 > 三珠エリアの文化財
三珠エリアの文化財
 幾多の文化財は、この町の中で、長い時を重ねひとつずつ丹念に織りあげられてきたものです。
幾多の文化財は、この町の中で、長い時を重ねひとつずつ丹念に織りあげられてきたものです。先人たちから伝えられた、かけがえのない歴史。
静寂のうちに遺されたそれぞれの文化財には、その時代ならではの人々の姿が映し出されています。
三珠エリアの文化財について
薬王寺
 薬王寺は、天平18年(746年)に行基が開基したと伝えられる寺で、現在は真言宗の寺院になっています。珍しい十一面観音が祀られ、甲斐三十三番観音巡礼の第一札所として、かつては多くの巡礼が寺を訪れました。客殿には、後陽成天皇の皇子「八之宮良純」に由来する
御座所
が伝えられています。良純親王は十八歳で得度し僧侶となりましたが、朝廷内の権力争いによって寛永20年(1643年)甲斐の国に流され、薬王寺には5年間滞在しました。寺はその後焼失し、現存の御座所は再建後につくられたものです。また、境内の
オハツキイチョウ
の大木は見事で、この種の木の北限にあたり生態学的にも注目されています。
薬王寺は、天平18年(746年)に行基が開基したと伝えられる寺で、現在は真言宗の寺院になっています。珍しい十一面観音が祀られ、甲斐三十三番観音巡礼の第一札所として、かつては多くの巡礼が寺を訪れました。客殿には、後陽成天皇の皇子「八之宮良純」に由来する
御座所
が伝えられています。良純親王は十八歳で得度し僧侶となりましたが、朝廷内の権力争いによって寛永20年(1643年)甲斐の国に流され、薬王寺には5年間滞在しました。寺はその後焼失し、現存の御座所は再建後につくられたものです。また、境内の
オハツキイチョウ
の大木は見事で、この種の木の北限にあたり生態学的にも注目されています。
古墳
 数々の古墳がつくられた曽根丘陵。この丘伊勢塚古墳陵に属する旧三珠町にも、円墳(
伊勢塚
・鳥居原狐塚)と前方後円墳(エモン塚・大塚)の古墳が残されています。古墳の中からは、馬具・鈴付腕飾り・直刀・六鈴鏡・甲冑・埴輪・須恵器など、興味深い出土品が発掘されています。特に、鳥居原狐塚から発掘された神獣鏡には「赤鳥(呉の年号)元年五月二十五日」(238年)の日付が記され、古墳鏡の中でももっとも古い部類に属しています。
数々の古墳がつくられた曽根丘陵。この丘伊勢塚古墳陵に属する旧三珠町にも、円墳(
伊勢塚
・鳥居原狐塚)と前方後円墳(エモン塚・大塚)の古墳が残されています。古墳の中からは、馬具・鈴付腕飾り・直刀・六鈴鏡・甲冑・埴輪・須恵器など、興味深い出土品が発掘されています。特に、鳥居原狐塚から発掘された神獣鏡には「赤鳥(呉の年号)元年五月二十五日」(238年)の日付が記され、古墳鏡の中でももっとも古い部類に属しています。
熊野神社の狛犬
 もともとは町内の各所にあった熊野神社ですが、大正期に合祀されて今日の
熊野神社
になっています。古い石像物としての様式を伝える狛犬も、合祀に関連して明治後期に元の社から移されたものです。つくり方は、粗削りでおおらか。まるで、当時の人々の素朴な信仰を表しているかのようです。狛犬の腹部には応永12年(1405年)の銘があり、狛犬の源流として全国でも珍しい貴重な文化財です。
もともとは町内の各所にあった熊野神社ですが、大正期に合祀されて今日の
熊野神社
になっています。古い石像物としての様式を伝える狛犬も、合祀に関連して明治後期に元の社から移されたものです。つくり方は、粗削りでおおらか。まるで、当時の人々の素朴な信仰を表しているかのようです。狛犬の腹部には応永12年(1405年)の銘があり、狛犬の源流として全国でも珍しい貴重な文化財です。
市瀬山光勝寺
承久2年(1220年)に開基した古刹光勝寺は、真言宗の寺院で甲斐三十三番観音巡礼の三番札所。本尊の千手観音像は運慶作と云われており、また、仁王門は町文化財指定されるなど、歴史的な美術品としても価値の高いものです。(なお、広目天、多聞天は指定されていません)。境内は、道路から奥まった高い位置にあり、いかにも山寺らしい、風雅な雰囲気につつまれています。
竪穴式敷石住居跡
 北原古墳群の一角にある、縄文中期の
竪穴式敷石住居跡。床面には平板状の石が敷きつめられ、二つの炉がつくられた珍しい住居跡です。この跡からは、土器片や石斧、宗教儀礼に使われたと推定される石棒などが出土しています。
北原古墳群の一角にある、縄文中期の
竪穴式敷石住居跡。床面には平板状の石が敷きつめられ、二つの炉がつくられた珍しい住居跡です。この跡からは、土器片や石斧、宗教儀礼に使われたと推定される石棒などが出土しています。
表門神社
 この
表門神社
は市川文珠とも呼ばれ、知恵文殊の神様として知られています。本殿は三間社流れ造りの建築様式で、桃山期の作風を残していますが、各部分の様式や棟札から、現在の社は江戸中期元禄8年(1695年)の造営であることがわかります。同じ境内にある神楽殿も同時期に造営されたもので、祭りの日には記紀神話に基づいた神楽が催されます。神社の中でもっとも古いものは、石鳥居。その意匠から鎌倉期のものと推定され、がっしりと重厚で風格のある鳥居です。
この
表門神社
は市川文珠とも呼ばれ、知恵文殊の神様として知られています。本殿は三間社流れ造りの建築様式で、桃山期の作風を残していますが、各部分の様式や棟札から、現在の社は江戸中期元禄8年(1695年)の造営であることがわかります。同じ境内にある神楽殿も同時期に造営されたもので、祭りの日には記紀神話に基づいた神楽が催されます。神社の中でもっとも古いものは、石鳥居。その意匠から鎌倉期のものと推定され、がっしりと重厚で風格のある鳥居です。
一条氏館跡
 別名上野城とも呼ばれる
一条氏館跡
。一条信龍は武田信虎の八男で信玄の異母弟にあたり、信玄の代、騎馬百騎をあずかる侍大将でした。しかし信龍の人間性は「伊達者にして花麗を好む性質なり」と甲陽軍鑑が記すように、荒っぽい甲斐の武将の中にあって特異なものでした。このような一条氏の館を見ることができるならば、きっと雅趣に富んだ美しい住居であったことでしょう。現在の歌舞伎公園・一帯が館跡とされています。
別名上野城とも呼ばれる
一条氏館跡
。一条信龍は武田信虎の八男で信玄の異母弟にあたり、信玄の代、騎馬百騎をあずかる侍大将でした。しかし信龍の人間性は「伊達者にして花麗を好む性質なり」と甲陽軍鑑が記すように、荒っぽい甲斐の武将の中にあって特異なものでした。このような一条氏の館を見ることができるならば、きっと雅趣に富んだ美しい住居であったことでしょう。現在の歌舞伎公園・一帯が館跡とされています。
一瀬桑
 かつて養蚕が盛んだった三珠町。
一瀬桑は、養蚕に不可欠だった桑の最良品種の親株です。この桑は明治34年、一瀬益吉によって二株発見されたもので、以後奨励品種として増殖され、全国の養蚕のために大きな貢献をしました。親株は今日でも大切にされ、一瀬氏の偉業を伝えています。
かつて養蚕が盛んだった三珠町。
一瀬桑は、養蚕に不可欠だった桑の最良品種の親株です。この桑は明治34年、一瀬益吉によって二株発見されたもので、以後奨励品種として増殖され、全国の養蚕のために大きな貢献をしました。親株は今日でも大切にされ、一瀬氏の偉業を伝えています。
写真が載っているものを青字で表しています
![]()