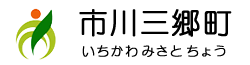城山烽火台跡
城山烽火台跡について
武田時代、国防警備のため、軍事連絡機関として各地要衝の場所に烽火台を置いた。富士川を挟んで南は南巨摩郡万沢
村の白鳥山を起点として、およそ一里くらいの見通しのつく山頭を選んでその施設をした。駿河国志に「駿河内房村に接する高山なり。又城取山という。永禄12年信玄駿河攻撃の時、此山に物見を架す、陣場、鞍掛、馬の脊、大皷、打揚山等の名が山中に存せり」となる。打揚山は、烽火台である。東西河内をぬって黒沢の鐘つき堂山から市川と山保との界の城山が最後であった。甲府要害城から望めば真南に当たっている。その時代跡部蔵人が警備したといい、武田滅後、徳川入国の時、先手の大洲が兼高が守兵を置いた。烽火を一名狼煙というのは狼の糞を焚くので、煙の乱れぬためであるという。
![]()