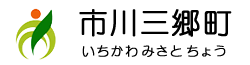文化財(史跡)
文化財(史跡)
内藤肥前守の墓
 内藤家は代々武田家に仕え、肥前守の父は俗称外記、先に昌資に作る、武田信虎公より一字を拝領して相模守虎資という。虎資の男内藤肥前守雅明武田家より九一色の守護を任ぜられ高萩に任す。現在地頭屋敷残る、法号は自観院性室宗見居士、弘治四年九月朔日卒去
内藤家は代々武田家に仕え、肥前守の父は俗称外記、先に昌資に作る、武田信虎公より一字を拝領して相模守虎資という。虎資の男内藤肥前守雅明武田家より九一色の守護を任ぜられ高萩に任す。現在地頭屋敷残る、法号は自観院性室宗見居士、弘治四年九月朔日卒去肥前守に三男五女あり
男 内藤孫三郎雅綱 肥前守を襲名光源院開基
内藤織部正昌行 後幕府に仕へ三百石扶持
内藤孫五郎義昌 垈村に住居
女 武田信虎 妾 一男三女あり 内藤 服という
武田六郎信基 主夫折
穴山伊豆信友室 梅雪の母也
称津美濃守元直室 宮内信政ノ母
内藤修理亮昌豊 室
伊勢塚古墳
 市川三郷町大塚、北原古墳群中の一基で、大塚地区の古墳群中もっともよく原型を残して、一般からも親しまれているのがこの伊勢塚である。基底は径36m、高さ8m、頂点の径18mである。頂点には伊勢大神を祠る石祠があり塚の名称の由来となっている。封土上には数本の大木があったがすべて伐採され、今は草地となっている。
市川三郷町大塚、北原古墳群中の一基で、大塚地区の古墳群中もっともよく原型を残して、一般からも親しまれているのがこの伊勢塚である。基底は径36m、高さ8m、頂点の径18mである。頂点には伊勢大神を祠る石祠があり塚の名称の由来となっている。封土上には数本の大木があったがすべて伐採され、今は草地となっている。一説には江戸末期に発掘を試みたが、崇りを恐れて原形に復し石祠を建立したといわれている。
エモン塚古墳
 市川三郷町大塚、道林古墳群の内の一基で、道林部落の南方丘上にあって、北側に押出川の溪流があり、自然の地形を利用した前方後円墳である。
市川三郷町大塚、道林古墳群の内の一基で、道林部落の南方丘上にあって、北側に押出川の溪流があり、自然の地形を利用した前方後円墳である。墳丘は松林となっており稲荷の小石祠がある。昭和初期の土木工事により、前方部はすべて失われた模様である。主軸の方向は東西と推定され、封土を切り取った高さは約7mばかりで、この部分より大形の「かめ」を発掘したといわれている。
道林古墳群中、封土を残す唯一の古墳である。エモン塚の名称は近くに一条林があり武田の一族、一条右衛門大夫信竜に由来するものと思われる。
狐塚
 市川三郷町大塚、田見堂及鳥居原古墳群(上ノ原)の北端にある円墳で、明治26、7年ごろ発掘されたもので、その発見された遺物がわが国考古学界の貴重な資料となったため、早くより学界の注目を受けた。
市川三郷町大塚、田見堂及鳥居原古墳群(上ノ原)の北端にある円墳で、明治26、7年ごろ発掘されたもので、その発見された遺物がわが国考古学界の貴重な資料となったため、早くより学界の注目を受けた。現存する部分は径18m、高さ1mほどの草地となっている。
伝えるところによると、竪穴式の石室であったらしい。付近に積み重ねてある材石に赤色の粉末が塗ってあるのがわかる。
出土した副葬品は、鏡二面、直刀三口、剣一口、銅鈴一個、滑石臼玉一個、須恵器若干、その他となっている。鏡二面の中の一つは内行花文鏡で、いま一つは四神四獣鏡で直径12.5cm、鏡面の反り0.4cm、鏡面は半円方角帯の方形内に各一字を造出していたものであるが、現在では「吉」の一字だけが判読できるのみである。また銘帯の全文も不明だが「赤烏元年五月廿五日」の九字ははっきりとわかる。(赤烏は呉の大帝の年号・西暦238)本邦発見の記年在銘鏡中もっとも古いものに属する。
竪穴式敷石住居跡
 市川三郷町大塚北区薬袋泰光氏の屋敷続きの西側、東南に面する傾斜地の畑地に、縄文時代中期の敷石住居跡がある。
市川三郷町大塚北区薬袋泰光氏の屋敷続きの西側、東南に面する傾斜地の畑地に、縄文時代中期の敷石住居跡がある。この地は北原古墳群の一角であり、付近一帯は縄文、弥生古墳へ続く遺跡の複合地帯である。
この住居跡の発見は昭和4年4月であり、竪穴には板状の石が敷きつめられ床を固めている。しかも屋内には二つの炉が築かれているめずらしいものである。また入口に近い所(屋内)に石棒(信仰の対象)が立ててある。出土品としては、縄文中期の土器片、石斧(打製磨製)たたき石等であった。
一条氏塁跡
 一、一条信龍のこと、一条信龍は武田信虎の八男、信玄とは異母兄弟で「甲陽軍鑑」に、甲斐源氏の一門の名族一条氏の名跡を継ぎ、旧一条の庄(甲府市東南部)を支配、信玄の代騎馬百騎を預る侍大将として活躍、永禄10年(1567)以降甲軍の副将格で信玄を補佐、天正10年(1582)年3月武田滅亡の直前、上野城にたてこもり、駿河路から侵入する徳川家康と戦ったが、子の信就とともに戦死したものと伝えられている。峡南を支配していた穴山信君が、家康の軍門に降っただけに、甲州の防波堤となって守ろうとしたわけだが、「軍鑑」は信龍について「伊達者にして花麗を好む性格なり」と記し、信龍が文武両道に秀でていたことをうかがわせる。
一、一条信龍のこと、一条信龍は武田信虎の八男、信玄とは異母兄弟で「甲陽軍鑑」に、甲斐源氏の一門の名族一条氏の名跡を継ぎ、旧一条の庄(甲府市東南部)を支配、信玄の代騎馬百騎を預る侍大将として活躍、永禄10年(1567)以降甲軍の副将格で信玄を補佐、天正10年(1582)年3月武田滅亡の直前、上野城にたてこもり、駿河路から侵入する徳川家康と戦ったが、子の信就とともに戦死したものと伝えられている。峡南を支配していた穴山信君が、家康の軍門に降っただけに、甲州の防波堤となって守ろうとしたわけだが、「軍鑑」は信龍について「伊達者にして花麗を好む性格なり」と記し、信龍が文武両道に秀でていたことをうかがわせる。二、一条氏塁跡、市川三郷町上野にあり、信玄の弟一条右衛門大夫信龍の城地であった。別に上野城とも呼ぶ。外壁は二級三級の自然の地形をなし、南方は山に寄って民家が点在、北は絶岸、西はゆるやかな丘陵に続く、本丸の頂上に牛頭天王を祭る。馬場、門前、物見塚等の地名も残り、お年寄りは「一条林」と愛称している。古府中塔岩に一条氏の館があった。
大塚邑水路新造碑および代官中井清太夫生祠
 昔から大塚河原は大雨の降るたび、笛吹川の水位が上がり、悪水路の水は逆行して田圃は水没するという憂き目をみてきた。このため甲府代官として着任した中井清太夫にお願いし、天明6年から天明7年春にかけて悪水路の大改修が行われた。このため村の指導者らにより甲府代官退任後の寛政9年に建碑された。
昔から大塚河原は大雨の降るたび、笛吹川の水位が上がり、悪水路の水は逆行して田圃は水没するという憂き目をみてきた。このため甲府代官として着任した中井清太夫にお願いし、天明6年から天明7年春にかけて悪水路の大改修が行われた。このため村の指導者らにより甲府代官退任後の寛政9年に建碑された。石祠らは高さ147cm(台とも)正面35cm、奥行32cmの角柱で上部が欠落している。又生祠は高さ100cm、正面48.5cm、奥行75cmである。
この碑と生祠は従来押出川右岸の7年の上の排水渠を見下ろすところに建てられていたが、現在は県営大塚排水機場の北隅に移されてあり「お水神さん」として現在もなお地域住民に祀られている。

生祠

石祠
![]()