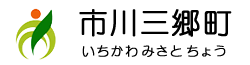薬王寺
薬王寺について
薬王寺
後陽成院第八ノ宮良純親王御座所

八ノ宮御座所
薬王寺は天平18年(746)聖武天皇の詔勅により、行基が開き観全僧都(カンゼンソウズ)の開山になる名刹である。
当寺の客殿の上段の間には、八之宮良純親王御座所(御座の間)の一部が保存されている。親王は、後陽成天皇の第八皇子で18歳で得度仏門に入り京都知恩院の門跡となったが、寛永 20年(1643)12月事情あって甲斐に流され、興因寺(甲府市)に12年間、続いて明歴元年(1655)に当寺にうつり5年間住んだ後、万治2年(1659)6月許されて京都に帰り、寛文9年(1669)66歳で没した。
当寺はその後焼失したが享保2年(1719)に再建にかかっている。そのなかで親王の遺跡を保存するため御座の間(親王が居住した一部)を客殿のそばに移築し享保9年(1726)に完成したことが袋戸棚の裏面に当山十九世(桓龍(カンリュウ))によって記録されている。
御座の間は客殿の上段の間(通称宮さん座敷)から東側に床を一段高くして移築してある。御座の間は方一間二畳敷で、天井には直径1mの十三弁の菊花紋がかたどられている。上段の間とは御翠廉で仕切られていておもむきがある。また、知恩院門跡尊超法親王の筆になる「儼然」 の額が揚げられていて落ち付きがあり、気品が感じられ往時をしのぶにふさわしいものである。
親王が、使用した品々の多くは、帰京の折持ち帰ったが、京についてから供の者をとおして当寺へ下げ渡しになった物が何品かある。現存する物は、町指定文化財「硯」をはじめ見台、脇息、網焼物菓子器、丁子風呂(香をたきこめる道具)等が保存され親王をしのぶよすがとなっている。
薬王寺のオハツキイチョウの雄株

薬王寺のオハツキイチョウの雄株
山梨はオハツキイチョウの宝庫であり、葉上に種子をつける雌株は八本ほど見つかっていて、そのうち身延町下山の上沢寺のオハツキイチョウは明治24年7 月、白井光太郎博士によって葉上に種子のできる事実をこの木によって発見され、学界に紹介された木で、その隣りの本国寺のオハツキイチョウとともに昭和4 年4月、国指定の天然記念物に指定された。
葉上に葯をつけるオハツキイチョウの雄株は、同町上八木沢(前記上沢寺の富士川の対岸)の山神社の境内にあり、明治29年4月17日、藤井健次郎博士によって発見され、これも珍奇なものとして広く欧米の学界に紹介され、昭和15年7月国の天然記念物に指定された。オハツキイチョウの雄株で指定されたものはこの木だけである。
ここ薬王寺にあるオハツキイチョウの雄株は、山神社の境内にある木についで二番目に発見された木である。発見者は旧三珠町誌の編集にたずさわっていた山梨植物同好会々長の秋山樹好先生で、発見当時(昭和51年)の「植物採集ニュース」にも掲載された
この木は寺の境内の南西側にあり、根本の周囲4.1m、目通り幹囲3.7m、枝張り東7m。西9m。南6m、北6.5m、樹高16mでかなりの大木である。葯の数が多い葉ほど変形が著しく、葉も小さくなる。また葯をつけた葉は一枚一枚落ちるのではなく、葉と雄花と葯をつけた葉とが叢生したまま落ちてくるのである。
![]()